定年退職をあと少しで迎えようとしている筆者がマイクロ法人を設立しようと思ったきっかけは、一番には、とあるネット記事を読んで会社を辞めた後の国民健康保険を試算してびっくりした事です。知識としてある程度知ってはいましたが、実際に計算した結果を見ると、「う〜ん、、、」ってなってしまったところです。
今までも結構な額の社会保険料を払ってきており、年金生活に入っても、高くなることはあっても安くなることはない、国民健康保険をずっと払わなくてはいけないのかと考えると「なんだかなぁ、、、」、と言う事でマイクロ法人設立を設立しようと考えた次第です。
そもそもマイクロ法人とは
マイクロ法人とは、従業員を雇用せずに、一般的には代表者自身が1人で事業活動を行う小規模な会社のことです。会社法などの法律で明確に定義されているわけではありませんが、このように認識されています。
近年、働き方改革や多様なビジネスモデルの登場を背景に、個人事業主が税金や社会保険料の節減などを目的にマイクロ法人を設立するケースが増えています。
マイクロ法人は、一般的な法人とは異なり、外部の株主や複数の従業員を置かず、事業活動のすべてを代表者1人が行います。しかし、法律上は一般的な会社(非公開会社)と同じ扱いであり、会社法に則った設立手続きや登記が必要です。一般的な法人が事業拡大や社会貢献を主な目的とするのに対し、マイクロ法人は株主への利益還元を必要とせず、節税を主な目的とすることが多い点も特徴です。
マイクロ法人と個人事業主との違い
マイクロ法人と個人事業主の最も大きな違いは、法人格の有無です。
マイクロ法人:法人格があるため、法人名義で契約や取引を行うことができます。
個人事業主:法人格がないため、個人名義での活動となります。
なお、働き方自体に大きな違いはありません。
筆者自身、設立の大きな目的は三つ!
マイクロ法人設立のメリットとデメリット
マイクロ法人設立のメリット
- 社会保険料の節減
マイクロ法人を設立する一番のメリットは、社会保険料を大幅に節約でき、手取りが増える可能性があることです。
個人事業主のみの場合、個人事業の年収に応じた社会保険料を納めることになりますが、二刀流としてマイクロ法人で少しだけ収益を上げるビジネスを行い、マイクロ法人の従業員として社会保険に加入することで、個人事業主側での社会保険加入が不要となり、最小限の社会保険料で済む場合があります。
また、法人の厚生年金・健康保険では、扶養家族分の保険料支払いが不要です。 - 税務上のメリット
マイクロ法人にすることで、個人事業主よりも税務上のメリットを受けられる場合があります。役員として会社から報酬を受け取ることで給与所得控除が適用され、所得税や住民税の節税につながります。
また、個人事業主としての消費税の納税義務が免除される可能性もあります。 - 社会的信用度の向上
マイクロ法人は法人登記を行うことで情報が公開されるため、個人事業主に比べて社会的信用度が高くなることが期待できます。
これにより、大手企業や金融機関との取引がしやすくなったり、法人を対象とした補助金や助成金を利用できる可能性があります。
また、法人名義で契約や取引を行うことが可能になります。 - 事業の柔軟性
個人事業主としての仕事とは別に新規事業を立ち上げる際(二刀流)に、マイクロ法人を設立することで、税額を抑えることができる場合があります。
マイクロ法人設立のデメリット
- 設立費用
マイクロ法人を設立するには費用がかかります。
株式会社の場合は約22万〜24万円(条件で変動)、合同会社であれば約6万円の設立費用が発生します。
株式会社の場合は定款認証に費用(約7万2千円〜9万2千円、条件で変動)がかかりますが、合同会社の場合は不要です。
会社設立時の登録免許税の軽減できる特定創業支援等事業についてはこちらから。
- 維持費用(ランニングコスト)
マイクロ法人を維持するためには費用が発生します。
法人住民税の均等割は赤字でも納付する必要があり、自治体によって異なりますが年間約7万円程度かかります。
また、税理士に決算申告などを依頼する場合は、別途専門家報酬として年間少なくとも約10万円程度かかることがあります。
なおバーチャルオフィスや電話受付代行サービスなどを利用する場合も、毎月の費用が発生します 。 - 事務手続きの煩雑さ
マイクロ法人を設立すると、個人事業主のときよりも経理業務や事務手続きに手間がかかります。
年に一度、マイクロ法人の決算申告を行う必要があり、貸借対照表や損益計算書などの作成・提出が求められます。
個人でこれらの書類を作成するのが難しい場合は、税理士に依頼することになり、その分のコストも発生します。 - 税務上の注意点
個人事業主と両立してマイクロ法人を設立する場合、個人事業とマイクロ法人の事業内容を明確に分ける必要があります。
同一事業とみなされると、意図的に所得を分散させて租税を回避していると疑われる可能性があります。
また事業活動の実態がないとみなされる場合(ペーパーカンパニー)、税務署から租税回避行為や脱税を疑われるリスクもあります。 - サラリーマンの場合の社会保険料
サラリーマンがマイクロ法人を設立しても、このケースではマイクロ法人設立による社会保険料の節約はできません 。
当たり前ですがサラリーマンは雇用元の会社で社会保険に加入しているため、マイクロ法人で社会保険料を支払うことはできません。
逆に、マイクロ法人から役員報酬を受け取ると、社会保険料が増える可能性もあります。
マイクロ法人設立を検討する際は、これらのメリットとデメリットを十分に理解し、検討している事業の状況や将来の展望などを考慮して慎重に判断することが重要です。必要に応じて、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
マイクロ法人を設立する流れ
マイクロ法人の設立にはいくつかの段階があります。ステップごとに説明します。
1:会社設立に必要な基礎情報を決める
まず、定款にも記載する会社設立に必要な基本的な情報を決定します。
「メモ(薄緑の枠内)」は筆者が検討している内容となります。
- 会社形態
株式会社か 合同会社のどちらかを選択します。マイクロ法人の場合は、登録免許税や定款認証にかかる費用が株式会社よりも安いことから、合同会社が基本的におすすめされています。
ただし、取引先からの信用が重要な場合や、銀行から多額の融資を受けてビジネスを行う場合は株式会社が推奨されることもあります。
会社法上は、株式会社、合同会社、合資会社、合名会社の4種類から選択可能です。
株式会社の設立費用は約22万〜24万円、合同会社は約6万円程度が目安です。
- 商号(会社名)
会社を識別するための名称を決めます。一定のルールを守り、他の会社と区別できるだけでなく、商標権を侵害しないような名称にする必要があります。
株式会社の場合は(株)またはカ)、合同会社の場合は(同)またはド)を商号に入れる必要があります。
- 事業目的
会社が行う事業の範囲を具体的に定めます。将来的に行いたい事業も記載できますが、設立時の事業目的は10項目以下にすると分かりやすくなります。
曖昧な書き方は避け、「投資業」ではなく「有価証券の売買及び保有」のように具体的に記載することが重要です。
- 本店所在地
会社の拠点の住所を決定します。賃貸事務所だけでなく、自宅やマンションの一室、バーチャルオフィスも本店所在地として設定可能です。
将来的な移転の可能性を考慮し、市区町村までの記載に留める方が良い場合があります。
- 資本金:事業を行うための元手となる運営資金です。ルール上は1円から設立できますが、100万円から857万円の間が目安 とされています。資本金が低いと法人口座開設時に信用が得られない可能性があり、857万円を超えると登録免許税が増加します。1000万円を超えると1年目から消費税がかかる など税務上の注意点もあります。資金が不足する場合は、資本金に加えて役員借入金を利用する方法もあります。
- 会社設立日:法務局に会社設立の登記申請をした日が会社設立日となります。土日祝日は法務局が休業のため、平日にする必要があります。毎月2日以降の早い平日を設立日とすること で、初年度の法人住民税の均等割を少し節約できる可能性があります。
- 会計年度:会社の会計上の業績を評価する期間で、通常は1年間です。会社が自由に設定できますが、設立日が6月2日であれば決算日を5月31日とする など、最初の事業年度をできるだけ長くすることが推奨されます。税理士と契約する場合は、3月決算や12月決算は繁忙期のため避ける方が良いでしょう。
- 役員や株主の構成:株式会社を設立する場合は、取締役を最低1名選定する必要がありますが、マイクロ法人では代表者1名が取締役と株主を兼任することが一般的です。合同会社の出資者は社員と呼ばれ、代表となる社員を決定します。
定款作成サービスについて、マネーフォワードとfreeeの比較記事はこちらから
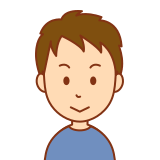
2025.4.12時点では、ここまでです。
2:法人用に使用する印鑑を作る
法人に必要な印鑑は、実印、銀行印、角印(請求書などに使用する確認印)の3つ です。楽天市場などで3点セット5000円程度で購入できます。登記申請の際には、法人の印鑑だけでなく個人の印鑑の押印も必要になります。
3:定款を作成する
定款とは、会社の根本的な規則を定めたもの で、発起人全員の合意が必要です。定款の作成には、紙定款と電子定款の2つの選択肢 があります。電子定款であれば印紙代4万円が不要 なため、電子定款が推奨されます。電子定款の作成には、マネーフォワード会社設立、freee会社設立、弥生の会社設立などの会社設立サービスを利用すると便利です।特にマネーフォワード会社設立は初心者にも使いやすいと評価されています。これらのサービスでは、順番に項目を入力するだけで電子定款のドラフトが完成し、サービス経由で行政書士に電子定款の作成を依頼できます(手数料約5000円)।定款には、事業目的や商号などの絶対的記載事項、定めがないと効力が生じない相対的記載事項、定めがなくても効力を失わない任意的記載事項があります。
4:公証役場で定款認証を行う
株式会社を設立する場合のみ、作成した定款を公証役場で認証してもらう必要があります。合同会社の場合は定款認証は不要です。認証には、作成した電子定款のデータや、発起人全員の印鑑証明書などが必要です。会社設立サービスを利用する場合は、サービスが手続きをサポートしてくれます।
5:資本金を払い込む
定款認証後(合同会社の場合は定款作成後)、定款で定めた額の資本金を払い込みます。発起人名義の銀行口座に払い込みを行い、通帳のコピーなど払込を証明する書類を保管します。会社設立サービスを利用すると、払込証明書の作成も可能です。
6:登記書類を作成し登記申請を行う
法務局に会社設立の登記申請を行います。登記申請には、登記申請書、登録免許税分の収入印紙を貼った納付用台紙、定款、発起人の決定書、設立時取締役の就任承諾書、設立時代表取締役の就任承諾書、設立時取締役の印鑑登録証明書、資本金の払込があったことを証する書面(払込証明書)、印鑑届出書、登記すべき事項を記載した書面もしくは保存したCD-R などの書類が必要です。これらの書類の多くは、会社設立サービスを利用することで自動的に作成できます。登録免許税は、資本金の額などによって異なりますが、合同会社の場合は資本金が857万円以下であれば6万円 です。登記申請の方法は、法務局の窓口に直接行く、郵送する、オンライン申請するの3つがあります。オンラインの会社設立サービスの中には、郵送での申請をサポートしているものもあります。
7:登記簿謄本と印鑑証明書を受け取る
登記申請が受理され、問題がなければ、通常1週間から10日程度で登記が完了します。登記完了後、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)と印鑑証明書 を法務局の窓口、郵送、またはオンラインで受け取ります。これらの書類は、法人口座の開設や各種手続きに必要になります。
8:各種行政への手続きを行う
会社設立後、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所などに対して、法人設立に関する各種届出 を行う必要があります。例えば、税務署には法人設立届出書や青色申告の承認申請書、年金事務所には健康保険・厚生年金保険 新規適用届などを提出します。これらの手続きには期限があるため、注意が必要です。
これらのステップを経て、マイクロ法人の設立が完了します।マイクロ法人の設立方法は、ブログでもさらに丁寧に解説されているとのことです。
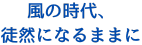





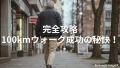
コメント