二十四節気の穀雨(こくう)は
- 意味:「穀雨」という名前は、「百穀を潤す春の雨」という意味を持っています。
春の雨が大地を潤し、種まきした穀物の成長を助ける時期であることを表しており、農耕民族にとっては非常に重要な節目でした。 - 時期:4月20日~21日頃、2025年は4月20日です。
- 季節:暦の上では春の終わり頃にあたります。実際には、地域によって気候が異なりますが、一般的には春らしい穏やかな気候が続く時期です。
気温が上がり始め、植物が芽吹き、花が咲き乱れる、生命力にあふれた季節です。 - その他:農家にとっては、種まきや田植えの準備など、一年の中でも特に忙しい時期です。
また暖かくなってくるので、夏服の準備を始めるのも良いでしょう。
新緑が美しい季節なので、ハイキングやピクニックなど、自然の中で過ごすのもおすすめです。
穀雨の期間は、さらに細かく3つの候に分けられています。
- 初候:葭始生(あしはじめてしょうず): 葦が芽を出し始める(4月20日~4月24日頃)
- 次候:霜止出苗(しもやみてなえいずる): 霜が降りなくなり、稲の苗が生長する(4月25日~4月29日頃)
- 末候:牡丹華(ぼたんはなさく): 牡丹の花が咲き始める(4月30日~5月5日頃)
さて時事ネタとして、4月17日のテレ朝ニュースから「プラチナNISA」にからんで、記事にしてみました。
【解説】高齢者向け「プラチナNISA」とは?金融庁が検討開始した新NISAのポイント
2025年4月、高齢者向けの新しいNISA制度「プラチナNISA」の創設が金融庁で検討されているという報道がありました。
本記事では、このプラチナNISAとは一体どのような制度なのか、その背景やポイントについて詳しく解説します。
結論から言うと、別にプラチナNISAを使って、毎月分配型投資信託を選ばなくても、証券会社にもよりますが、楽天証券のような定期売却サービスを利用すれば、今のNISAを長期的に積み立てて、必要になったら売却すれば良いのでは、と考えます。
ただし、スイッチングは魅力的ではありますね。
プラチナNISA創設検討の背景
現行のNISA制度は、少額からの投資で得られる利益を非課税にする制度であり、家計の資産形成を支援することを目的としています。2024年末時点で口座数は2560万以上、18歳以上の4人に1人が開設しており、長期の積み立て投資を前提としているため、利用者は若い世代が中心です。
しかし、70〜80代の高齢者からは「リスクは無理」「積み立てできない」「先が短いから」といった慎重な意見や制度への不満の声が上がっていました。
こうした背景から、自民党や証券界を中心に、高齢者にも使いやすい制度を求める声が高まり、金融庁が高齢者の投資促進を目的とした新しいNISA、すなわち「プラチナNISA」の創設を検討し始めたのです。
プラチナNISAの主な特徴:毎月分配型投資信託が対象に?
プラチナNISAの大きな特徴として検討されているのが、毎月分配型の投資信託を対象とする 点です。
現在のNISA制度(つみたて投資枠・成長投資枠)では、長期の資産形成という趣旨に合わないとして、毎月分配型の投資信託は原則として対象外となっています。
しかし、プラチナNISAでは、高齢者が年金と合わせて投資信託の分配金を月々の生活費に充てたいというニーズに応えるため、毎月分配型を対象に加える方向で検討が進められています。
毎月分配型の投資信託は、運用で得られた利益の一部を毎月支払う仕組みですが、運用が低迷した場合には元本の一部が取り崩されて分配金が支払われることもあります。
毎月分配型投資信託のメリットと懸念点
高齢者にとって、毎月定額の分配金を受け取れることは、生活費の足しになるというメリットが考えられます。まとまった金融資産を保有しているものの、年金だけでは毎月の生活費が不足する場合、毎月分配型投資信託を保有し、「分配金受取型」を選択することで、毎月のキャッシュフローを補填できる可能性があります。
しかし一方で、毎月分配型投資信託には以下のような懸念点も指摘されています:
- 元本取り崩しのリスク: 運用状況によっては、分配金が利益からではなく元本から支払われる可能性があり、資産が減少してしまう恐れがあります。
- 手数料: 毎月分配型投資信託には、相対的に手数料が高いものが多い傾向があります。
- 誤解: 投資家が分配金の一部である「元本払戻金」を利益の分配金と誤解し、「高い利回りが得られる」と誤認する可能性があります.
- 分配金再投資の非効率性: 毎月分配型を選びながら「分配金再投資型」を選択する場合、分配金を受け取るたびに源泉税が引かれるため、複利効果を十分に得られず、非合理的な投資行動となる可能性があります.
- 販売手法: 高齢者を狙った不適切な販売が行われる可能性も懸念されています。「毎月お金が入ってくる」「新しいNISAの対象」といった甘い言葉で勧誘され、仕組みを十分に理解しないまま契約してしまうトラブルも起こり得ます。
プラチナNISA創設に向けた今後の検討
金融庁は、プラチナNISAの制度設計にあたり、上記のような毎月分配型投資信託の特性を踏まえ、高齢者が安心して利用できるような仕組みを検討すると考えられます。
例えば、対象となる毎月分配型投資信託の条件(デリバティブ取引の制限、信託報酬の上限など)や、金融機関からの情報提供の強化、分かりやすい説明の義務化などが検討される可能性があります。
また、長期にわたって積み立て投資をしてきたNISA口座の資産を、高齢者がプラチナNISAの毎月分配型投資信託に移行できる「スイッチング」(一度だけ)についても、一定の条件下で認められる方向で検討されているとの報道もあります。
さらに、NISAの「つみたて投資枠」の年齢制限についても見直しが検討されており、旧制度の「ジュニアNISA」のように、18歳未満でも積立投資が可能になるような制度も議論されているようです。
まとめ
プラチナNISAは、高齢者の投資意欲を高め、資産を活用する新たな選択肢を提供する可能性がある一方で、毎月分配型投資信託の仕組みやリスクを十分に理解しておく必要があります。
制度の詳細については、今後の金融庁の発表や税制改正の動向を注視していくことが重要です。
筆者自身、今回の「トランプショック」もあり、そこまでして高齢者に投資を進めなくても良いのではと、想う次第です。
(上記は、現時点で報道されている情報を基に作成した解説であり、今後の制度設計によって内容が変更される可能性があります。)
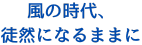






コメント